お互いを探り合うような日々が続いている事にリーマスは深い溜息を吐いた。
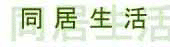
一緒に暮らす事になってから半月が経過した。自分たちの仲は非常に旨くいっているようだ。ようだ…というのはおかしな表現だと、リーマスは苦笑を漏らす。それでは誰か別の人間の話のようだからだ。もちろん、これは紛れもなく自分たちが陥っている事態の事なのだが。
けれども、リーマスはこの事を自分が他人事のように感じる理由もきちんと分かっていた。
そもそも、リーマスはジェームズを失ってから12年間、一度も彼に会っていなかった。それもその筈、彼は洋上の監獄に囚人として捕らわれていたからだ。当時の事を思うと、その頃とは別の意味で胸が痛い。リーマスはぼんやりと窓の外を見つめた。
この古い一軒家は周りに家がない。あるのは、鬱蒼とした森と小さな小川だけだ。窓の外では黒い髪の青年…シリウスが必死に洗濯物と格闘している。久しぶりに再会した時より数段ましになった顔色の友人は、少年の頃の面影を取り戻しつつあった。指名手配中の脱獄死刑囚とは似ても似つかない容貌になってきている。
リーマスは物干し竿にシーツを引っかけるのに、どっちの方向でした方が効率的かしきりに頭を捻っている友人の無邪気な横顔を凝視する。
こんな日々は想像していなかった。
自分はもう在りし日の貴重だった全ての物を失ったと覚悟していた。自分に残っているのは大切な友人が残していった忘れ形見だけで、それだって、遠くからこっそり守ってあげられることだけを望んでいたに過ぎなかった。リーマスは暗い室内の影からそっと外をうかがう。
今、彼の手元に残っている貴重な一人が目の前にいる。まるで現実感がなかった。だから、何だか他人事の様な感想を覚えたのだ。
彼はほんの1年前には自分の憎悪の対象だった。それは否定しようのない事実だ。リーマスは突然襲ってき罪悪感に胸を掻きむしられた。
シリウスは何も言わない。彼が何を思っているのか分からない。いっそ言って欲しいと思う。自分を責めて欲しいと。どうして、自分を信じてくれなかった、助けてくれなかったと。彼は言わないだろうということは容易に想像できたけれど、リーマスはそう弾劾して欲しかった。
言ってくれれば自分は彼に色々な話を聞くことができる。そして、助けに行けなくてごめん、信じられなくて本当に悪かったと謝ることができるのに。それなのに、彼は何も言わない。リーマスは爪を噛んだ。そんな癖はしばらく忘れていたが、彼の出現によって、自分の時間が逆行しているような気がした。
シリウスの屈託のない明るさの裏の哀しみを掴む事が出来たのは、もう一人の友人だけだった。それは彼にしか許されていない特権だったのだ。
「ジェームズ、私に力を貸してくれ」
リーマスは思わず天を仰いだ。
シリウスは洗濯したてのシーツを何とか抑えて物干しにしがみついた。風が凄くてなかなか竿に干すことが出来ないのだ。こんな時、すかさず助け船を出してくれそうな友人に視線を向ける。リーマスはじっとこっちを見ていたが、その視線は自分ではなく別の物を、或いは別の時間を見ているように見えた。シリウスは軽く溜息を漏らす。
だいたい、自分はリーマスが生きているとは思っていなかった。
大切な友人から託された彼を自分は死なせてしまったと思いこんでいた。12年前、彼は自ら命を絶っただろうと諦めていた。ジェームズが死に、ピーターが自分に殺されたという偽りにとうてい太刀打ち出来ないだろうと思っていたのだ。
穴があったら入りたい心境とはこういう事をいうのだろう。シリウスはその事を思うたびに心の中でリーマスに謝った。
彼はシリウスが想像したより、ずっとずっと強い人だったのだ。
犬の姿でホグワーツに潜伏していた時、遠目に彼の姿を見た衝撃が忘れられない。自分を陥れる罠かと一瞬思ったくらいに予想外だった。彼は随分くたびれ、病みやつれていたけれども、リーマスをリーマスたらしめていたあの独特の笑顔だけは変わらなかった。あの無色透明な微笑みを、昔から自分はたいそう気に入っていたのだ。そうジェームズにも話した事がある。彼は笑って
「あんな哀しそうな笑い方はないよ」
と言っていたけれども、それでも自分はあの微笑みが好きだった。
その微笑みが変わっていなくて嬉しかった。変わらなかった事がどれほど大変だったか、予想できるのは自分だけだろうとシリウスは思っている。
もちろんそれだって本当の彼の苦労は分からない。
たった一人になって全て失って、希望も未来もなく、裏切りと欺瞞の中で彼が感じた孤独はアズカバンで自分が鬱々と感じていたそれよりずっと重かったに違いない。結局の所、自分はあの監獄で時間を止めてしまったけれど、この12年間彼は生き続けていたのだ。シリウスはシーツと格闘しながら、再度溜息を漏らした。
言ってくれればいいのに…と思う。お前が悪いんだと、どうしてピーターなんかを信じて自分を信じてくれなかったんだと、何故あの土壇場になってあんな最悪な選択をしたのだと、どうしてジェームズを守りきれなかったのだと。
そう言ってくれたら自分はリーマスに今までの話しが聞ける。酷い目に合わせてすまなかったと言えるのに。彼はけして自分を責めはしないだろうとシリウスは分かっていた。彼は他人を責める前に自分を責めるのだ。そういう人だった。
それでもシリウスは何度も話を切り出そうとしたのだ。けれども、「思うことがあるのなら言ってくれないか」などと言おう物ならリーマスは驚いた様な顔をして
「何の悪戯をしたんだい?パッドフット」
と笑うくらいが関の山だろう。それくらいはシリウスにだって予想がついた。シリウスはリーマスの微笑みの奥を掴む事はできない。それは別の友人の役目だったからだ。
「助けてくれ…ジェームズ」
思わず唸った。
食事時に二人は沈黙を守った。せっかく二人で食べているのだから何か会話が欲しい所だったけれど、会話するには何かの話題がいる。静かなこの家に何のニュースソースもなく、毎日当たり前に暮らしている二人にとって特に言葉に乗せなければならない話題が見つからない。
互いに聞きたい事はあったけれども、それを聞き出す権利が自分にあるのか、それを聞くことで相手を傷つけたりしないかと思い、聞くことが出来なかった。
「そういえば…」
シリウスは意を決して言葉を紡いだ。リーマスはその声に驚いてびくりと肩を震わす。その動作でシリウスの言葉は止まった。彼はパニックに陥る。しまった!タイミングが悪かったと。そして、顔色の変わったシリウスを見てリーマスも慌てた。せっかくシリウスが気を利かせてくれたのに、暢気に食事に専念しているからこんな事になるのだと。
二人はしばらく顔を見つめ合っていたけれど、気まずい雰囲気の中、溜息を同時に吐いた。
「あーーー…その…そうだ。ハリーは元気にしているかな」
シリウスが苦し紛れに名付け子の話題を出した。この話題なら自分たちには共通の想いがある。リーマスは彼の助け船に乗ることにした。
「そうだね、今頃夏休みだからきっとおばさんの家に居ると思うよ」
「そうか。あの腐れマグルの家か。苦労させるな」
「大丈夫だよ。あの子はあれで結構したたかだ。流石ジェームズの息子だよ」
その名を口にした途端リーマスは後悔した。彼らが一緒に過ごすようになって半月、その名は半ば意図的に禁句だった。その名を出すだけで、相手の心を大きく乱す事を予想していたからだ。実際、二人はせっかく盛り上がった会話をまたも中断する羽目になった。
「・・・・・」
「・・・・・」
二人はお互いに相手に悪かったと思い俯いた。酷く居心地が悪いと感じる。
けれども二人とも相手の姿が見えなくなると不安になるのだ。何しろ1年前まで失ったと思っていた大事な友人だ。そして、二人とも相手がいついなくなるか、これは幻で自分の幻想なのではないかなどと愚にも付かない想像に駆られてしまうのだ。
「ああっ。もうやめた!!!」
突然叫んだのはやはりシリウスだった。驚いてリーマスが彼を見つめると、シリウスは不敵な笑いを口の端に浮かべた。そんな表情をすると、彼はちっとも昔と変わらない。リーマスは、ふとそこにあの負けん気が強く、何事にも妥協しなかった少年が立っているような錯覚に襲われた。
「オレを殴れ」
けれども、流石に彼の口から出た言葉には咄嗟に反応できなかった。相変わらず突拍子のないシリウスの言動に、目を白黒させるだけだ。
「シリウス…。君が何を言いたいのかさっぱりわからないのだけれど…」
リーマスは仕方なく腕組みしているシリウスに向かってそう呟いた。彼の言葉にはさっぱり脈絡がない。まぁ、昔からシリウスの突然の言葉がさっと読みとれる事など皆無だったから、さして変わったわけではないが。それでも…この言葉には何の心当たりも無かった。
「分からないのか?違うだろう。お前にはその権利があるんだ。それで、さらっと今までのわだかまりが無くなるわけではないだろうが、ちょっとはスッキリするだろう。」
権利とかわだかまりとかそういった単語からリーマスはシリウスがようやく何を言いたかったのか推理できた。何て事はない、自分たちは同じ事を思い悩んでいたのだ。
一緒に暮らし始めて半月、ちょっと会話すれば理解出来た事を避けて、無駄に気詰まりな時間を過ごしてしまった。リーマスは吹き出したくなるのを何とか抑えた。ここで笑ったらシリウスが怒り出すのは火を見るより明らかだ。彼は腹筋に最大限の力を入れてどうにかその衝動を堪えた。
シリウスは神妙な顔でそんなリーマスを伺っている。彼は結構リーマスに殴られているので、その拳が見かけよりずっと強いのを知っている。奥歯を噛みしめてリーマスの反応を待った。
「分かった。それじゃ目を瞑ってくれるかい」
リーマスがそう棒読みした時、シリウスは緊張のあまり彼の目の前に居る人物の瞳が、昔、悪戯を思いついてキラキラしていたのと同じ色に染まっているのに気が付かなかった。シリウスは真剣な表情で頷きそっと目を閉じた。
リーマスはその目をあっさり閉じたシリウスの思い切りの良さに苦笑する。殴られるのを覚悟の上でここまで予備動作も無く目を閉じる彼の潔さに感心した。そして、久しぶりに見る友人の姿をじっくり観察する。
彼は元々、昔からシリウスの顔を眺めるのが好きだった。
長い睫がくっきりと影を落とす様子などは何度見ても飽きないと感心してたものだ。ジェームズにもよくそう言った。彼は苦笑して「まるで女の子を褒めるみたいだ」とぼやいた。シリウスの容姿は神様が作った最高芸術品だとリーマスは思っている。アズカバンの無惨な生活で一時は壊滅的なダメージをうけていたけれど、まるで大英博物館で修復したみたいに元に戻っているのがおかしかった。それで、思わずまじまじと彼の顔を凝視していた。
困ったのはシリウスである。彼だってべつに痛いのが好きな訳じゃない。何時あの強烈なパンチが向かってくるか戦々恐々としているにもかかわらずその気配がない。なかなか、何時来るか分からない痛みを待つというのは辛い物があるのだ。シリウスは内心溜息を吐いた。こんな嫌がらせをするようになるなんて、リーマスも性格曲がったなぁ。などと考えていたけれど、いくら何でもものには限度がある。
シリウスが盛大に文句を言おうと口を開きかけた時、その頬に微かに何かが触れた。それは柔らかく温かかった。
その感触には覚えがあったが、今ここでされる謂われのないものだった。一瞬の間にそれは離れていったが、間違いなくそれはリーマスの唇だった。その事にようやく思い至った。
慌ててシリウスは目を開いた。
目の前に在る友人の瞳からは涙が流れていた。シリウスはぎょっとして息を飲む。
「リーマス…」
途方に暮れたような自分の声に更に困惑してシリウスは彼の名を呼んだ。
「ごめん。最近涙腺が緩いんだ」
「いや、何も謝ることじゃない」
何とかシリウスはそう返事をしたけれど、果たしてその言葉が正しかったのか自信は無かった。もっと気の利いた事を言えればいいのに…と己の不器用さを悔しく思ったが。
「君の顔を見ているとね、シリウス。取り戻せない物など何もないという気がするよ。実際はそんな事ないって分かってるけど、どうしても還ってこないものだってあるのも知ってるけど、それでも…諦めなければ何時かまた、望んだ物を手にれる事は可能なんだね」
「リーマス…」
「君が今ここに居てくれて良かった。帰ってきてくれて本当に良かった」
はらはらと透明な涙がリーマスの頬を伝う。シリウスはそれを何だかざわざわした気持ちで見つめた。そんな風に静かに流れる涙を見るのはもう何年前の事だっただろう。よく覚えていない。それでも、彼はそれを止めたいと思った。だから、ついとその長い指をのばして、彼の頬をぬぐった。
そんなシリウスの仕草にリーマスはくすぐったそうに肩を揺らす。それがまた懐かしくてシリウスは笑った。思えば、こんな風にたわいなく笑い合うのはこの家にきて初めての気がした。彼はようやく一心地ついた気分になった。
自分一人でどこかに潜んでいたらこうはいかないだろう。彼は心から目の前で微かに微笑む古い友人の存在を喜んだ。
「オレも…うん。お前が居てくれて良かったよ。こうして生き残ったからには楽しい方がいいからな」
「全くだね。そんな事も忘れてしまうなんて、おかしいな」
「仕方ないさ」
お互いに苦笑を漏らす。
シリウスは、そういえば…と先ほどの感触を確かめるように頬に手を当てた。
「ところで、さっきのは何だったんだ?」
シリウスとしては当然の疑問だ。ところが、リーマスは明後日の方を向きながらいたって簡潔に
「キス」
と答えるだけだった。昔より格段に性格のよくなった友人に頭を抱えながらシリウスは更に食い下がる。
「だから、何で!?」
「そりゃ、殴って欲しいって言ってる人に仕返しするのに、殴ってもしょうがないじゃないか。嫌がらせだよ」
ぐうの音も出ないシリウスにリーマスは笑う。
「昔から、君の顔が好きだったんだ。近くで見たら急にしたくなった」
その答えにシリウスが目を白黒させるのが面白くてリーマスは声を出して笑った。
「いいじゃないか。減るもんじゃなし」
「そりゃぁ、そうかもしれないが…うーん」
首を捻るシリウスに更に笑みを深くしてリーマスが笑う。その笑顔を見てシリウスはちょっと思った。
ああ、ジェームズの奴、この笑顔を知ってたんだな…と。だから、あの笑顔を哀しい顔だと言ったのだと思い至った。
そして、シリウスもこっちの方が格段にいいと思うのだった。
この事があってから二人はぽつぽつとお互いの12年間の話をするようになった。
シリウスはあまり語ることを持たない。毎日が恐ろしいくらいの反復だったとどこか遠くを見るように言った。リーマスは逆にあんまり沢山の事が在りすぎて一度には無理だから、少しずつ話すよと穏やかに言い出した。
そして、二人は夜遅くまで語り合った。それは昔懐かしいグリフィンドール寮でのたわいない会話を思い出させる夜だった。
にゃかむら@勝手に追記
そうそう、こちらのシリウスさんは脱獄してから1度
先生にパンチを貰って吹っ飛んでいなさるのですよ。
(先様SS参照)当方の先生はそれを見て大変に
憧れたそうです(危)
私ならこんな愛らしい短編は人にあげたりはしません!
単独鹿の愛護団体の方といえば一番に思い浮かぶのは
かんだ様なのですが、鹿の方というのは皆辛抱強い方
ばかりです。
決してラインを超えられず、強制もされず、さりとて
諦めたりはなさらない。振り返るとニッコリ「鹿」と
囁かれる。現代に蘇った徳川家康がそこに!!と思いました(無礼)。
あ、ええ、ジムリリ書きます。おやくそくいたします。
↑ホトトギス……。
記念品、本っっ当ーにありがとうございました。
かんだみのり様のサイト「夜寝る前に謳う歌」 はこちら。
BACK